こんにちは!ライターの岸井アオイです。
突然ですがみなさんは毎年初詣には行きますか?私は毎年欠かさず神社に初詣に行っています。
今年のお正月にもいつも通り神社へ参拝に向かったのですが、家に帰ってから届いた年賀状を宛名別に仕分けしている時に、ふと疑問に思うことがありました。
「神道の人って喪中期間に参拝できるのかな?」そこからさらに疑問は広がります。
「神道の人も喪中はがきを出すのかな?」「そもそも神道と仏教では喪中の期間って同じなのかな?」などなど…気なることがあるとすぐに解決したい私は、さっそくそれらの疑問について調べてみることにしました!
この記事では神道の喪中期間、喪中期間の参拝のルール、喪中はがきについてなど、私のように神道に詳しくない人でも分かりやすいように紹介していきたいと思います。
せっかくなので、神道とおなじく日本人にとってなじみの深い仏教と比較しながら説明させていただきます。
基本的なことを知っていれば、いざ神道のお知り合いができた時に失礼がなくなりますよ!
神道の喪中期間はどのくらいある?
そもそも「喪中」とは何なのか?というところから説明しましょう。
神道における喪中とは、家族や近親者に不幸があった時に死の穢れ(けがれ)が他の者に移らないよう、外部との接触を絶つという意味で遺族が外部との接触を避けるというものでした。
喪中の間は結婚式などの慶事への出席を控え、亡くなった人をしのんで過ごすのが良いとされています。
さらに喪中は「忌」と「服」に分けられます。
「忌」とは、亡くなった人を悼む期間で、「服」とは喪服や喪章を付けて喪に服す(社交的な行動を控えて身を慎む)期間のことを言います。
この2つの期間を合わせて「喪中」と言います。
喪中の場合、亡くなった人との続柄によって期間が違っているようです。
忌日数と服日数も故人との間柄によって異なります。
戦前には「服忌令(ぶっきれい)」という法律によって詳しく忌と服の日数が決められていましたが、現代では土地や家庭の宗教観によって異なる考え方が定着しているようです。
明治7年に太政官より布告された忌服期間では、以下のようになっています。
<忌日数>
| 亡くなった人の間柄 | 日数 |
| 父母 | 50日 |
| 夫 | 50日 |
| 妻 | 20日 |
| 嫡子 | 20日 |
| 嫡子以外 | 10日 |
| 兄弟姉妹 | 20日 |
| 祖父母(父方) | 30日 |
| 祖父母(母方) | 30日 |
| 孫 | 10日 |
| おじ、おば | 20日 |
| 従兄弟 | 3日 |
| 甥、姪 | 3日 |
<服日数>
| 亡くなった人の間柄 | 日数 |
| 父母 | 13ヶ月 |
| 夫 | 13ヶ月 |
| 妻 | 90日 |
| 嫡子 | 90日 |
| 嫡子以外 | 90日 |
| 兄弟姉妹 | 90日 |
| 祖父母(父方) | 150日 |
| 祖父母(母方) | 90日 |
| 孫 | 30日 |
| おじ、おば | 90日 |
| 従兄弟 | 7日 |
| 甥、姪 | 7日 |
神社本庁によると、戦前までは「忌」の期間はもっとも長い父母で50日、「服」は13ヶ月だったとされています。
特に慣例がない場合「忌」は50日まで、「服」は1年間とするのが現代では一般的なようです。
仏教の49日法要にあたるのが神道では50日祭とされており、その50日祭が終わると忌明けという扱いになります。
一方で仏教では亡くなった人は7日に1回、合計7回の審判を受けてどの世界に転生するかが決まるという死生観があります。
そのため神道のように個人をしのんで悲しむ期間(喪中)という概念が本来はないのですが、審判が終わる49日までは神道同様に忌とし1年間は喪とすることが一般的になっています。
実際に親族の葬儀に参列するにあたり、学校や会社を休まなくてはならなくなりますが、その日数は官公庁などで戦後に忌引きの期間が定められ、「忌」の期間は配偶者で10日間、父母では7日間とされています。
ただ、勤務先などの就業規則によって休める日数は変わる場合がありますので、確認が必要です。
神道の人は喪中の間、初詣には行けない? 鳥居をくぐってもいけないの?

喪中期間、神道の人は神社への参拝をどうするのでしょうか?
初詣には行けるのでしょうか?とても気になるところですよね。
一般的には50日祭にあたる忌明けまでの間は神社への参拝はもちろん、鳥居をくぐるのも控えた方がいいと言われています。
まとめると以下の通りになります。
・50日祭が終わるまでの「忌中」の間にお正月がある場合、初詣は控えた方がいい。
・忌明けまでは鳥居もくぐらない。
・必要があって忌中に参拝やお宮参り、合格祈願などをしたい場合は、柏手(かしわで、手を叩く動作)の際に音を出さずに行わなければならない。
例)
「2礼・2拍手・1礼」の、拍手の際は静かに2回手を合わせて音が出さないようにする。
・ただし50日祭が終わって忌明けしていれば、「服」の期間中であっても神社に参拝してもいい。
神社によっては「服」の期間が明けるまでは参拝を避けてほしいと考えるところもあるようなので、事前に確認しておくといいでしょう。
ちなみに、お寺の場合は亡くなった人に新年のあいさつをするという考え方を取っているので、喪中のお参りも問題ないと考えられているようです。
死を穢れとして忌むべきものとしてとらえる神道に対し、仏教では上で説明したようにどちらかというと死を肯定的にとらえます。
こちらの動画では、「喪中の時の初詣は控えるべき?」という質問に、お葬式消費者相談のプロの方が答えてくれています。
神社・お寺への参拝についても教えてくださっていますので、ぜひご覧ください。
【youtube動画】喪中の時の初詣は控えるべきですか? 市川愛の「教えて!お葬式」vol.19
宗教観の違いがこんなところにも出ているのは興味深いですね。
神道の人は喪中はがきを出すの?
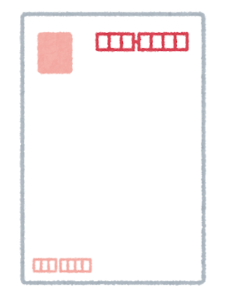
まず喪中はがきとは何かというと、年賀状を出さないということを相手に伝えるあいさつ状です。
一般的に喪中はお祝い事や宴席を避けるのが習わしとされているので、「新年明けましておめでとうございます」というようなフレーズが入る年賀状は、基本的には避けた方がいいとされます。
神道では故人が亡くなってから13ヶ月の間が喪中に該当するので、故人が亡くなった年の新年を迎える前に「今年は年賀状を送れない」ということをお伝えする喪中はがきを送ります。
「喪中欠礼はがき」とも言われるように、新年のあいさつを欠くことを伝えるお知らせなので、亡くなった人と深い関わりのあった人には忘れずに送りましょう。
基本的には避けた方がいい年賀状ですが、お仕事の関係などでどうしても年始のあいさつが必要なケースもありますよね。
そんな時には「年始状」をオススメします。
年始状とは、「謹賀」や「賀正」や「おめでとうございます」といったお祝いの言葉を使わずに書く年始のあいさつ状です。
お祝いのフレーズが入る年賀状とは違い、新年のあいさつのみをお伝えする年始状なら喪中でも送ることに問題はありません。
○年始状で使用する挨拶の文例(喪中でも使用して問題ないもの)
「謹迎新年」
「昨年はお世話になりました」
「年始のご挨拶を申し上げます」
など
○年賀状で使用する挨拶の文例(喪中では使用できないもの)
「賀正」
「謹賀新年」
「明けましておめでとうございます」
など
この他にもお世話になった感謝の言葉や、近況報告を一緒に書くのも問題ありません。
「賀・慶・祝・寿」などのおめでたい言葉を使わずに年始のあいさつをお伝えするのであれば、喪中期間に送っても構いませんよ。
まとめ
いかがだったでしょうか。
喪中は「忌」と「服」とに分けられていて、仏教と神道では日数が異なるというのは興味深い発見でした。
神道では忌明けまで神社へお参りできませんが、50日祭が終わった後は参拝しても大丈夫という扱いになります。
一方で仏教ではとくに参拝を禁じているルールはありません。
仏教と神道では死に対する考え方が違うので、参拝へのスタンスも違うというのも面白いですね。
またお祝い事を避ける喪中の間、年賀状は出せないので喪中はがきを送ります。
どうしても年始のあいさつが必要な場合は「年賀状」ではなく「年始状」で代用できるというのもポイントですね。
その際にはおめでたい言葉は避け、新年のあいさつのみをお伝えする言葉を選ぶようにしましょう。
日本人にとってなじみの深い神道ですが、いざ調べてみると新しい発見が多くて驚きの連続でした。
日本の街にはいろんなところに神社がありますよね。
お散歩のついでに神社に立ち寄り、神社の人にお話を聞いてみると新しい気付きがあって面白いかもしれませんよ。











