今年も来年の年賀状のデザインなどを考える時期がやってきました。
年賀状は毎年の事ですし、おめでたい事なのでそんなに難しく考えずに送っている方もいると思います。
一方で意外とわからないのが喪中はがき、送る時は?送られた側は?
そんな疑問を解いて、不安を取り除いていきましょう。
目次
喪中はがきはいつごろ出せばいいの?
喪中はがきは近年、年賀状が出せないことを伝えるはがきで、正式名は「年賀欠礼の挨拶状」と言います。
年賀状を出す前に届ける、でも出来れば年賀状に住所など書いてしまう前に届く方が良いです。
早すぎても、送られた方が忘れてしまいますのでご注意を。
喪中のはがきの出し方
日程で言うと、11月初旬から12月初旬ぐらいまでが好ましいです。
12月15日から郵便局の特別扱い期間が始まるので、それより後に届いてしまうと年賀状を出している可能性があります。
ただ、年末に不幸があった場合は除きます。
年内に喪中はがきが出せなかった時は、寒中見舞いで身内の不幸を知らせれば大丈夫です。
喪中はがきに一筆添えるのはマナー違反ですか?
「喪中はがきには個人的なコメントやメッセージを書いてはいけない」と云うマナー本が多いですが、「告別式ではお世話になりました」など、お世話になった方や親しかった方に一筆添えるのは良いと思います。
現代、ほとんどが印刷による対応で、味気がありません。
手書きで一言書いていると少しほっとしますね。
故人についてのことを書くことは良いのですが、「呑みに行こう」「遊ぼう」「結婚しました」など、遊びの予定やお祝い事などは控えて下さい。
これだと、喪に服しているかわからないからです。

喪中はがきを受け取ったら、どう対処すればいい?
喪中はがきを受け取って、
「年賀状を出さなくて良いのは知っているけど、後どうすれば良いのかわからなくてほったらかしにしている。」
「喪中と知らずに年賀状を送ってしまった。」
という方がいらっしゃると思います。
そんな時どうすれば良いの?
そういう場合は、年が明けてから寒中はがきを出すのが丁寧です。
お詫びやお礼、近況報告など。厳密な決まりごとはないので、ご自身の言葉で自由に書いて大丈夫です。
相手はあくまで喪に服している方なので、くだけすぎない様に気をつけてくださいね。
寒中見舞いは1月7日以降、1月下旬までに出されるのが一般的です。
喪中の方に出す寒中はがきのデザインは写真やイラストも使って大丈夫ですが、派手すぎないように気をつけて下さい。
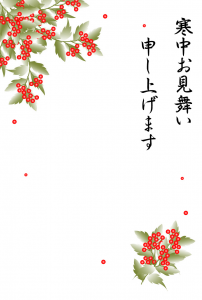
パソコンでの喪中はがきの作り方。喪中用のはがき、喪中用の切手ってあるの?
ハガキは普通の郵便ハガキでも、市販のハガキ専用紙でも大丈夫ですが、くれぐれも、年賀はがきだけは買わないように気をつけて下さい。
弔事用の切手もあり、「葦に流水模様」の切手が郵便局で手に入ります。
喪中ハガキも寒中はがきと同様、色やデザインが派手にならなければ写真やイラストを入れても大丈夫です。
モノトーンのイメージが強い喪中ハガキですが、紫やブルー系、ポイントに明るい色を使っても良いとされています。
挿絵に使う花にも、それぞれに意味があります。
「菊」は洗浄、「蓮」が神聖、「百合」は純潔、「水仙」は神秘、「菫」が誠実
昔から日本にある花がやはり風情や趣があり美しいです。
はがきソフトがあれば簡単にパソコンで喪中はがきを作成できます。
はがきソフトをお持ちでない場合、インターネットで喪中はがきのテンプレートを探していただければ、ワードでも作成できます。
喪中はがきを作成する手順です
① 喪中はがきテンプレートをダウンロードします。
いろいろなサイトがありますので、お気にいりの1枚を見つけてください。
② テンプレートをwordで開き、メッセージを入力します。
③ ワードの用紙設定がはがきに成っていることを確認します。
④ 喪中用はがきに印刷します。(印刷する時にプリンターの用紙設定も確認してください)
親が亡くなりました。親の個人的な友人にも喪中はがきを送った方がいいの?
喪に服し、新年の挨拶が出来ないのは故人ではなく、喪中はがきを出すご本人なので、基本はご本人の知り合いに送ります。
ですが、親御さんの友人で亡くなったことを知らない方には、報告も兼ねて喪中はがきを送るのも一つの方法です。
亡くなったことを知らない方から年賀状をもらった場合は、寒中見舞いを出して報告すればいいでしょう。
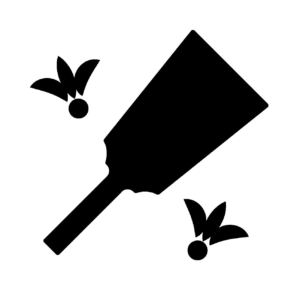
喪中はがきは、送る時の基本マナーさえ守ればそんなに難しいことではありません。
送る側も受け取る側もポイントを押さえ相手に失礼が無いようにしたいですね。











